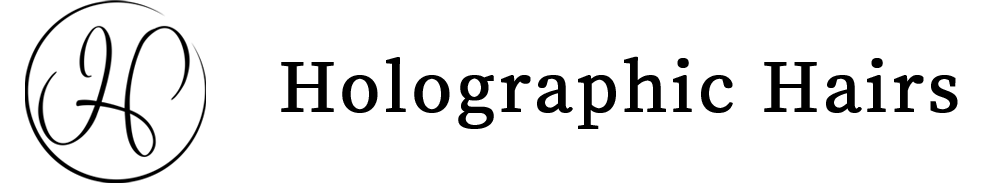電卓にはCPUが入ってる? いつ誕生し、どんな仕組みなのかを分かりやすく解説
※本記事の一部には AI を用いて構成や文章の整理を行っています。

「電卓ってCPUが入っているの?」
「電卓の超小型版がコンピューターなの?」
「電卓からコンピューターが進化したの?」
そんな素朴な疑問は、実は“計算機の歴史”そのものにつながっています。
結論から言うと、電卓とコンピューターは同じ祖先(計算機)から進化した“兄弟”のような存在です。どちらも「01の世界で計算をする機械」であり、仕組みの根本は驚くほど共通しています。
この記事では
なぜ電卓がここまで安くなったのか
を分かりやすく解説します。
🧮 電卓の中にCPUは入っている?
結論:入っています。
ただし、パソコンのCPUのような高機能なものではなく
**「電卓専用の超シンプルなマイクロプロセッサ(ICチップ)」**です。
- 四則演算用の回路+簡単な制御回路
- 電卓に必要な最低限の演算機能
- 電力消費が極めて小さい
- 100円電卓でも1チップで完結
多くの安価な電卓は「COB(Chip On Board)」という、
黒い樹脂で固められた小さなチップが基板に配置されています。
🕰️ 電卓の誕生はいつ?
電卓が“電子的な姿”で登場したのは 1960年代 です。
電卓の進化タイムライン
- 1960年代前半:トランジスタ式電卓が登場(机サイズ)
- 1967年:電卓専用IC誕生(シャープ、TIなど)
- 1970年代:小型ポータブル電卓が普及
- 1980年代:低価格化が進む
- 1990年代以降:1チップ化&100円ショップに並ぶレベルへ
💰 初期の電卓はいくらした?
衝撃の価格推移です。
| 時代 | 値段 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1960年代 | 数十万〜数百万円 | オフィス向けの高級機器 |
| 1970年代前半 | 数万円〜十数万円 | 一般企業にも普及し始める |
| 1980年代 | 数千円 | 家庭にも広まる |
| 現在 | 100〜1,000円 | ほぼワンチップで超低コスト |
最初期はPCよりも高価でした。
📦 初期の電卓は大きかった?
はい、とても。
1960年代の電卓は…
- タイプライターサイズ
- 重量10kg以上
- デスク専用で持ち歩き不可能
1970年代
- A5〜文庫本サイズに小型化、電池駆動可能
現代
- 手のひらサイズで超薄型
🧓 電卓の寿命はめちゃ長い
電卓は驚くほど壊れにくいです。
- 低電圧・低発熱
- 可動部がない
- 専用チップは故障が少ない
普通に 20〜30年動く ものが多いです。
学校で“昭和の電卓”が現役なのも納得。
まとめ
- 電卓にも**専用CPU(マイクロプロセッサ)**が入っている
- 電卓の登場は1960年代
- 当時は巨大で数十万〜数百万円の高級機器
- 半導体技術により急速に小型化&低価格化
- 現在は100円でも買える
- 寿命は20〜30年以上と非常に長い
電卓の進化とコンピューターの関係を、できるだけやさしくまとめてみる
「電卓って、コンピューターの小さい版みたいなもの?」
こういう素朴な疑問から、電卓とコンピューターの歴史をたどってみると、とても面白い流れが見えてきます。
■ 1800 年代:人力 → 機械へ
昔、人は計算を“そろばん”や“手計算”でやっていました。しかし 1800 年ごろから、歯車やばねで動く“機械式の計算機”が登場します。
ハンドルを回すと、歯車が動いて桁が繰り上がる…そんなアナログな仕組みです。
これはまだ「電気なし」で動く計算機でした。
■ 1900 年代前半:電気が入ってくる
電気が使われ始めると、機械式の動きをモーターで補助したり、ボタン式になったりして、計算が速くなっていきます。
ただしこの頃はまだ「重たい」「大きい」「高い」が当たり前。
■ 1940〜50 年代:コンピューター誕生
第二次世界大戦がきっかけで、電気だけで動く“電子式コンピューター”が登場しました。
巨大な建物ほどのサイズで、計算しかできないのに 電卓どころじゃないほど大きい。
でも原理としては、今日の PC と同じで「0 と 1 の電気信号」で考えるしくみがここで生まれました。
■ 1950〜60 年代:電卓の“コンピューター化”が始まる
コンピューターに使われていた電子部品が小型化していき、
「電気だけで動く電卓」=“電気式計算機” が誕生します。
日本だと CASIO を含む多くのメーカーが参入し、
どんどん 小型化・軽量化・低価格化 が進んでいきます。
■ 1970 年代:手のひらサイズの電卓に
半導体(ICチップ)が小さく、安く作れるようになると、
ついに“ポケットに入る電卓”が登場。
ここから今の電卓の形に近づきます。
■ そして現在:
電卓は「計算に特化した、小さくて正確なコンピューター」と言えます。
逆にコンピューターは、電卓のような“計算のしかた”をもっと複雑な形に発展させた機械です。
つまり…
電卓とコンピューターは同じ根っこを持つ“兄弟”みたいな存在。
コンピューターの進化の途中に電卓があり、電卓の進化にもコンピューターの技術が活かされてきた。
そう考えると、身近な電卓も、実はすごく深い歴史の上に成り立っているんですよね。